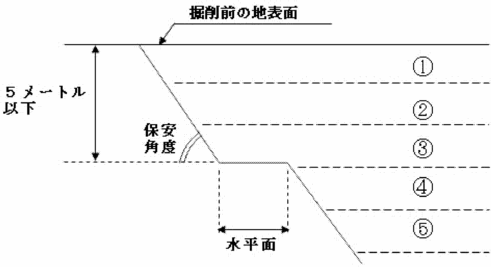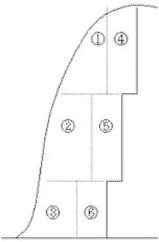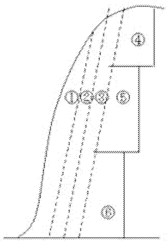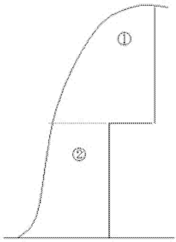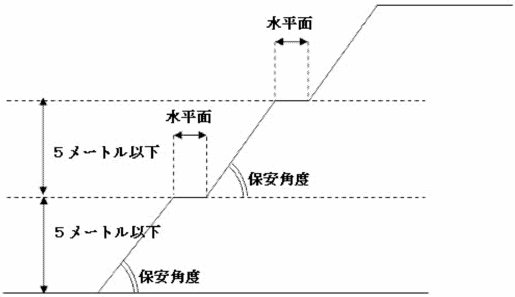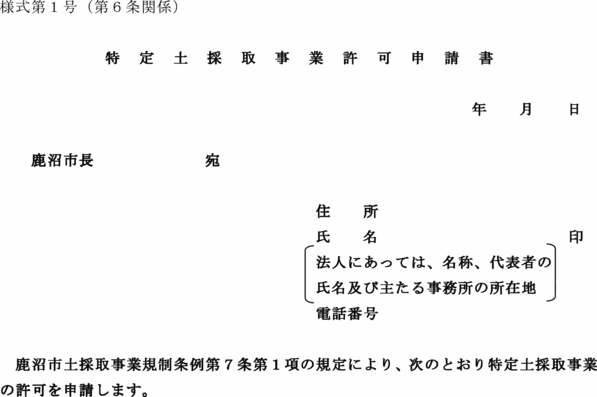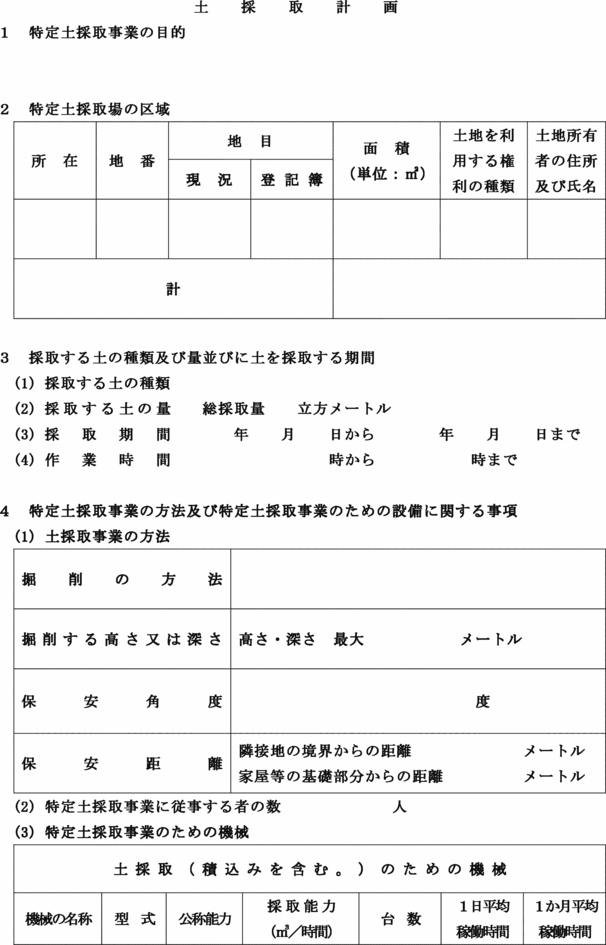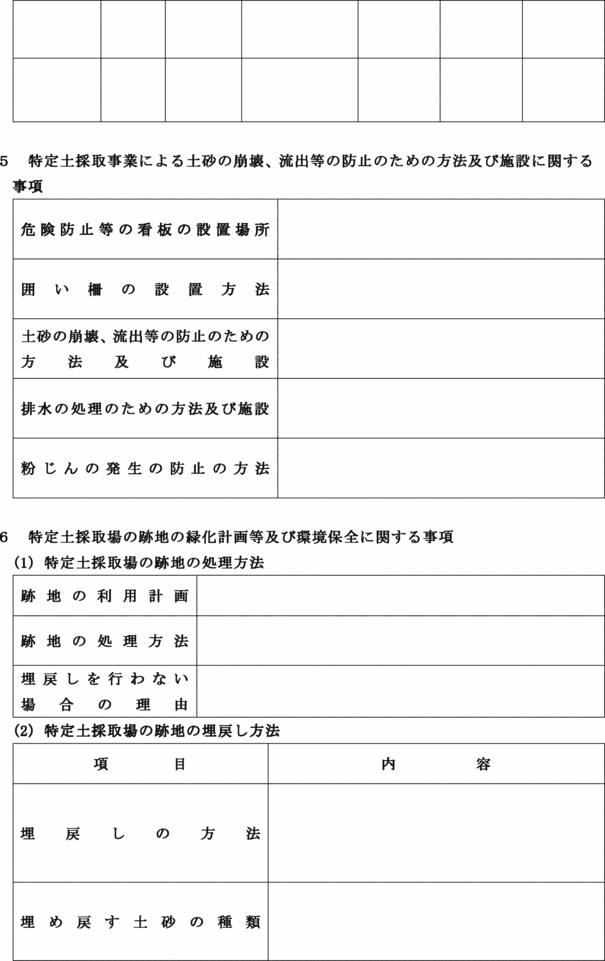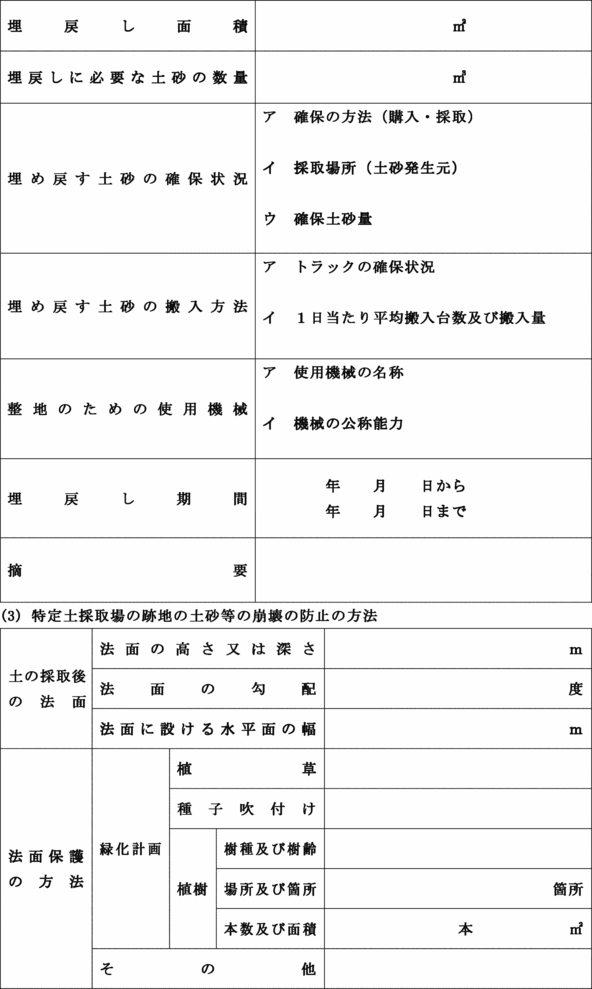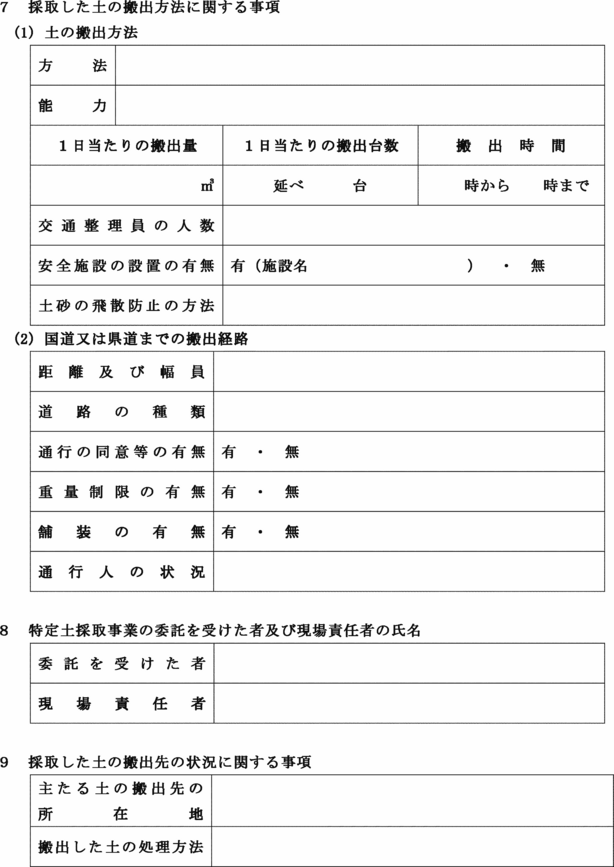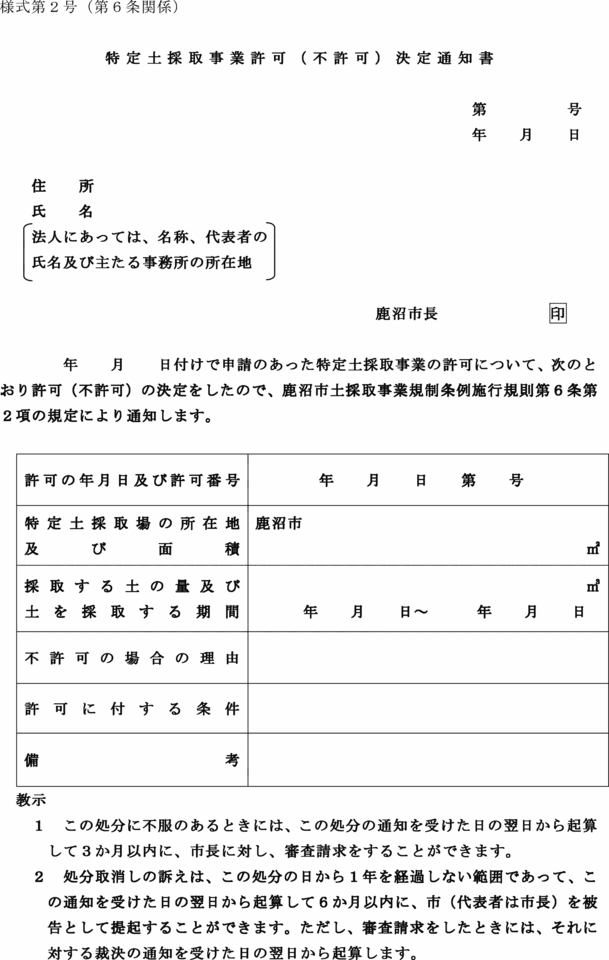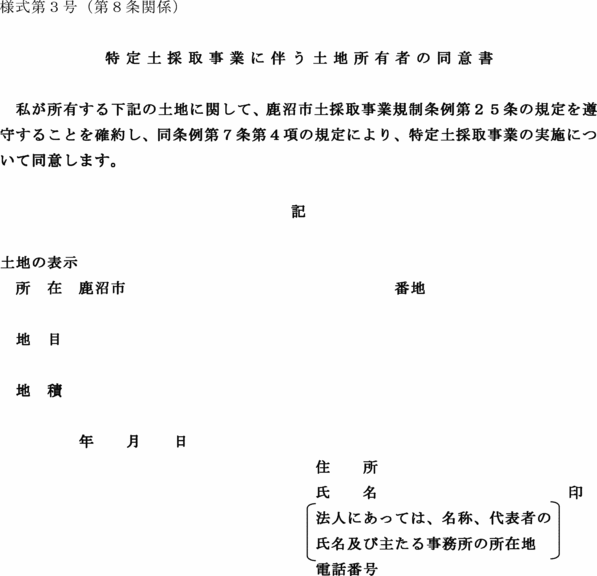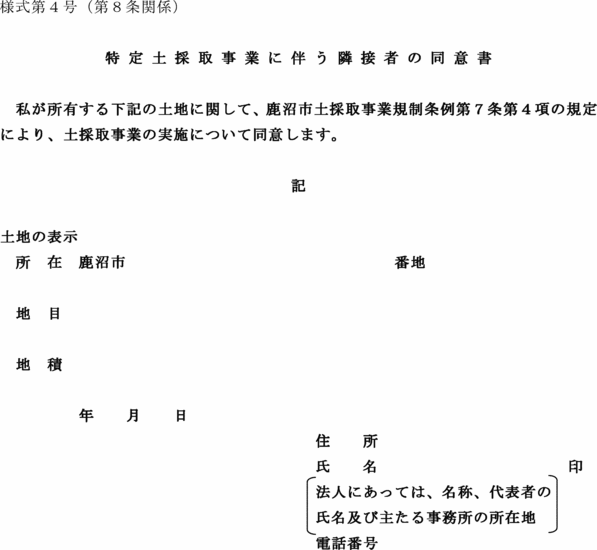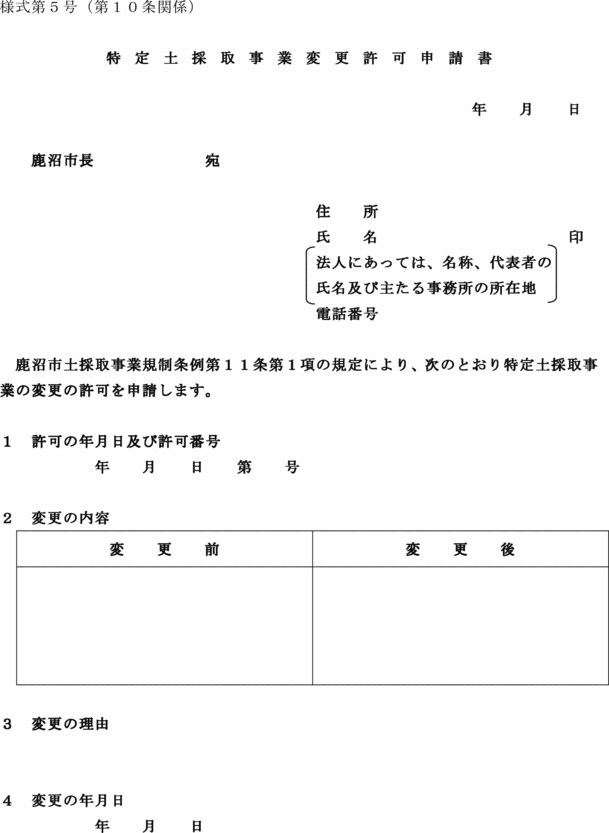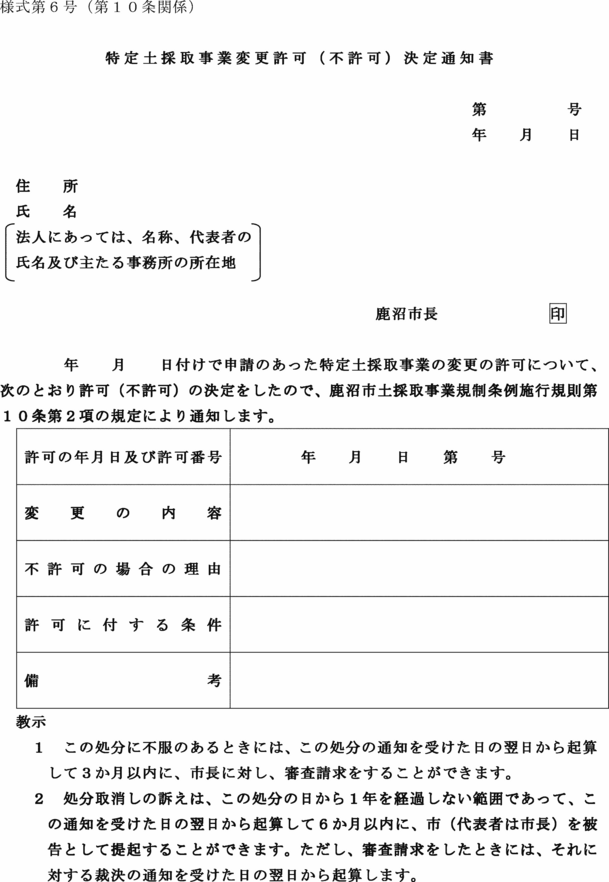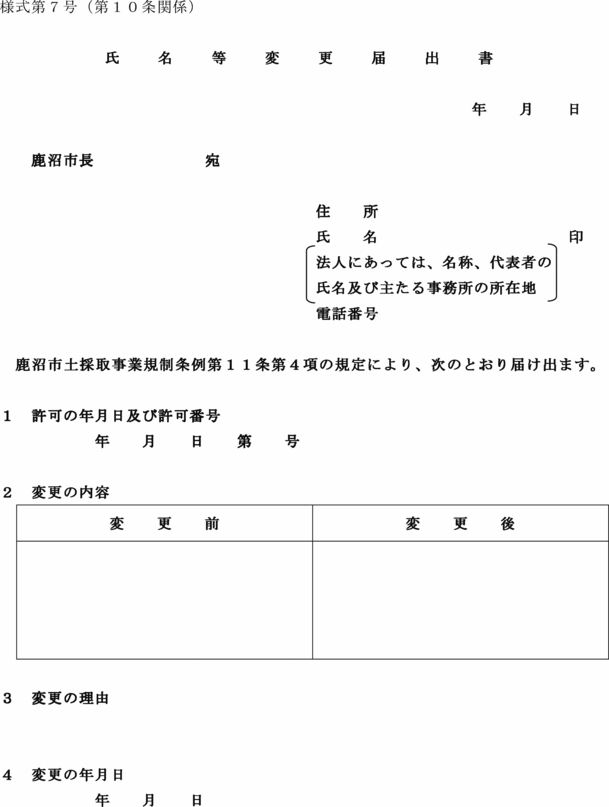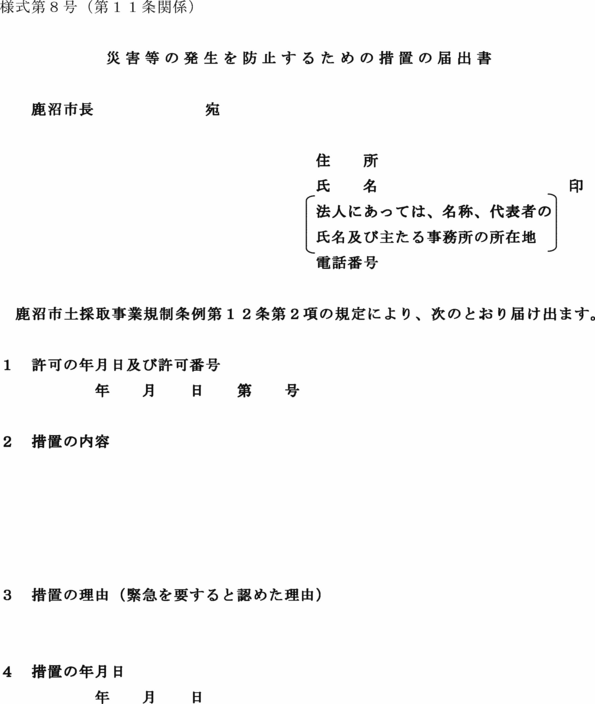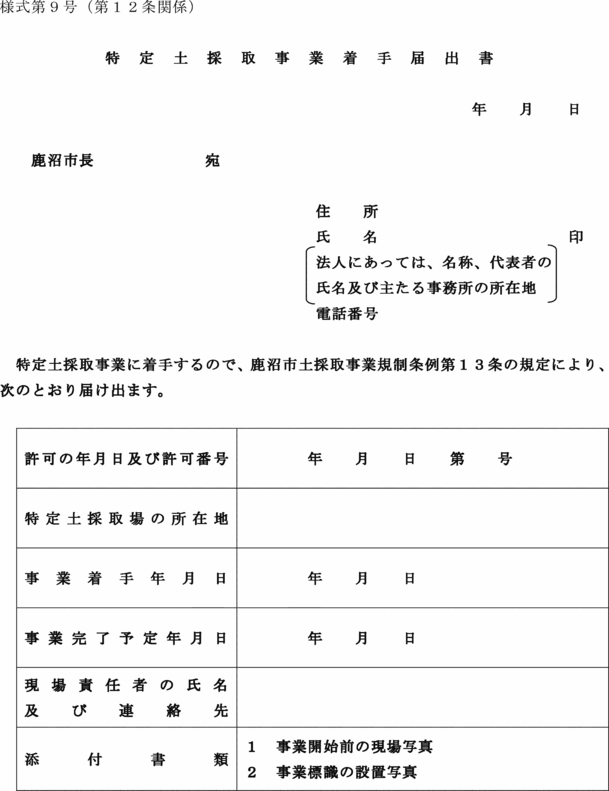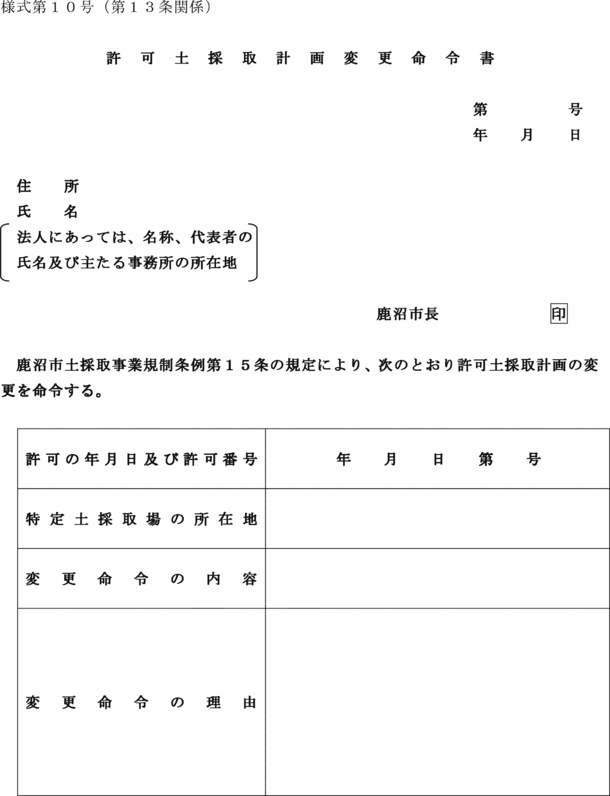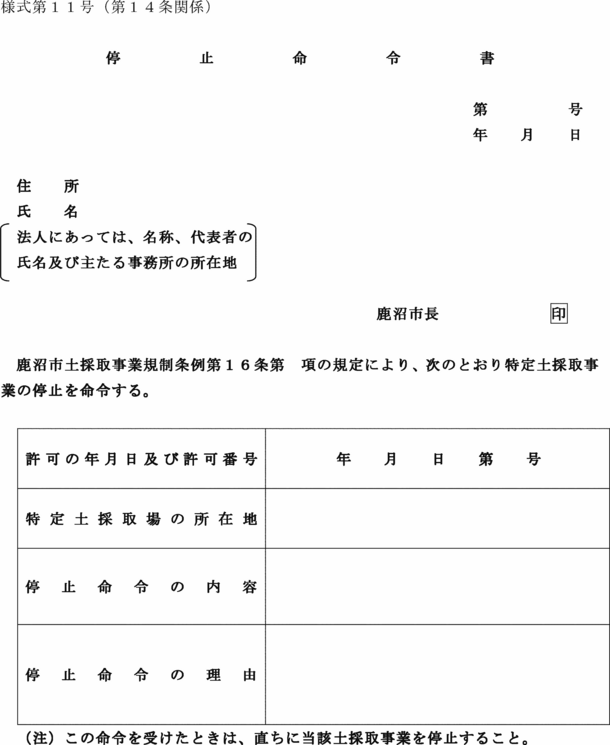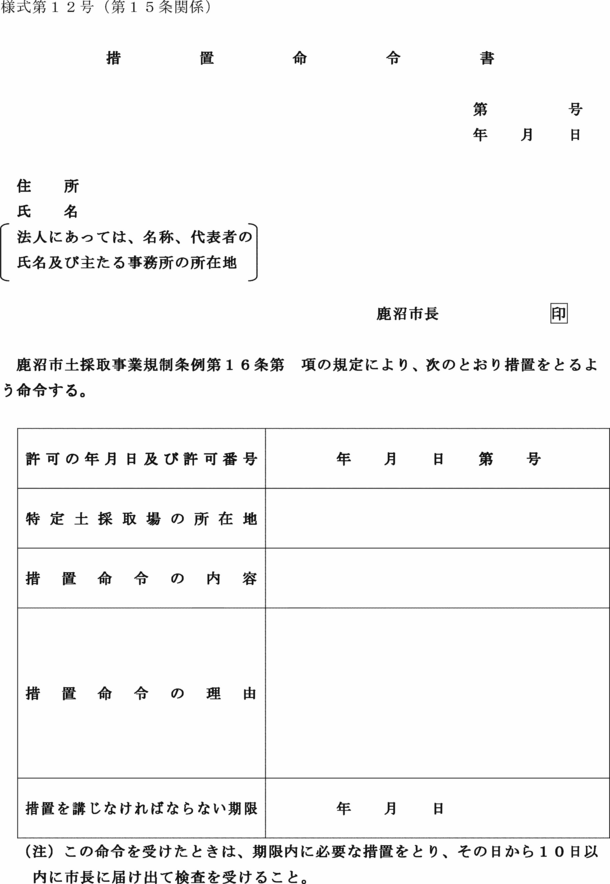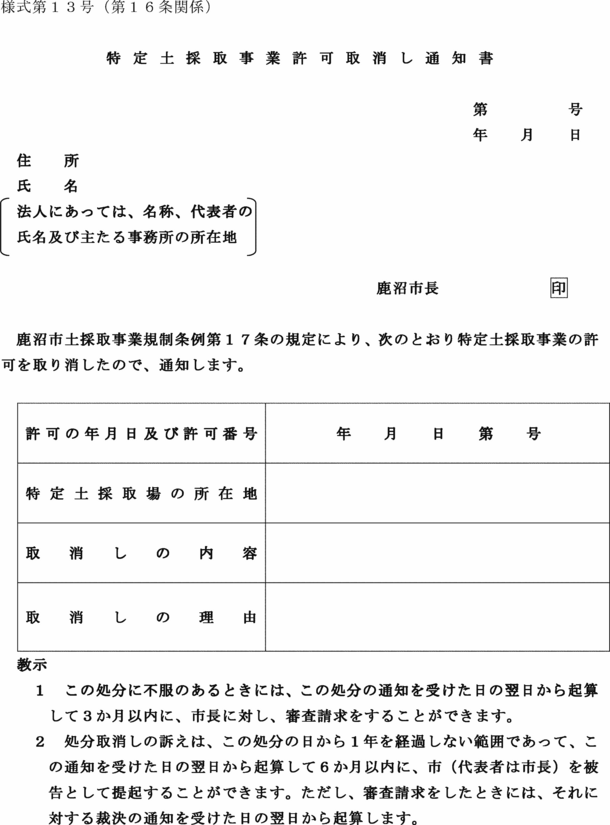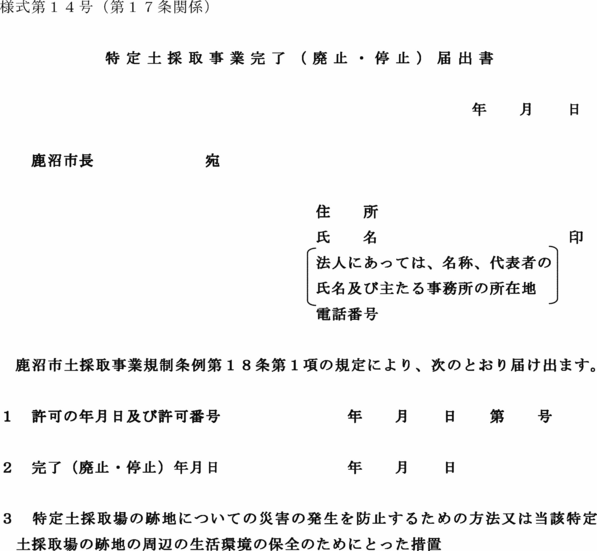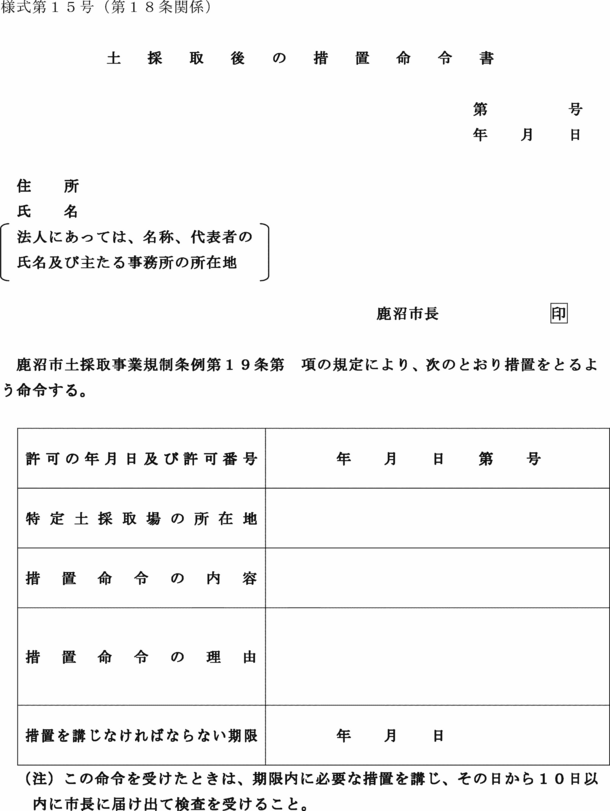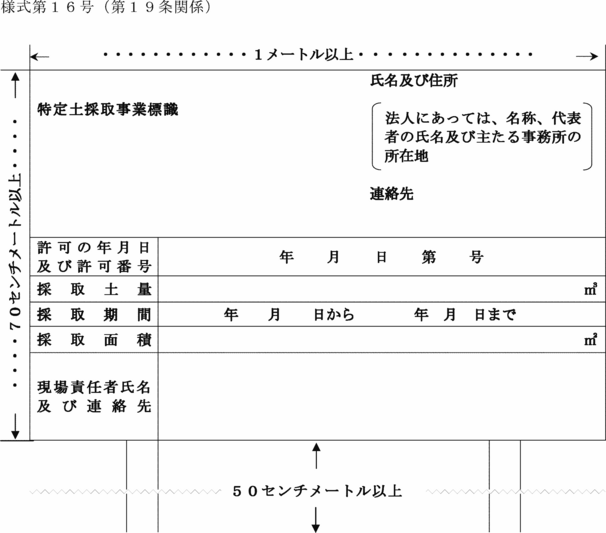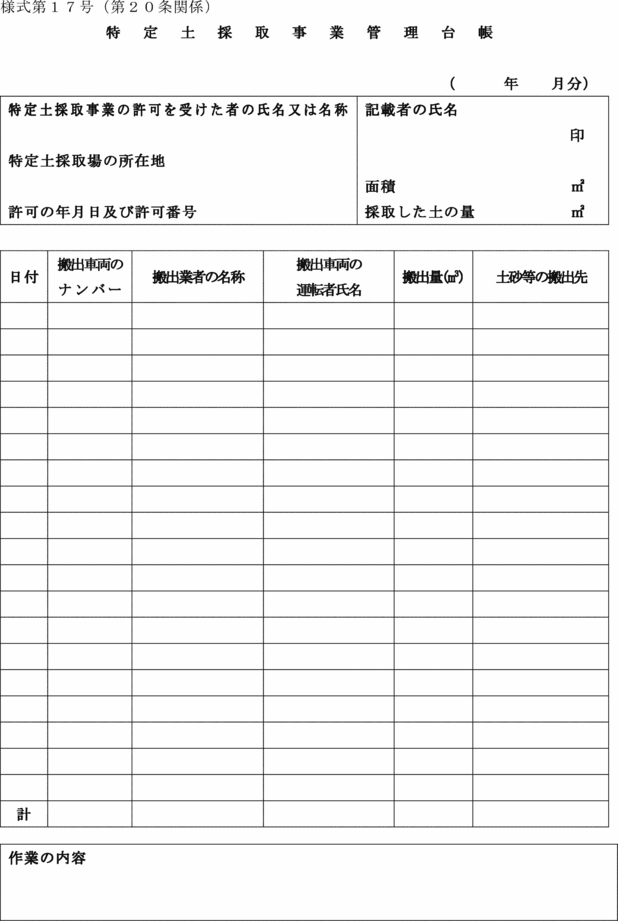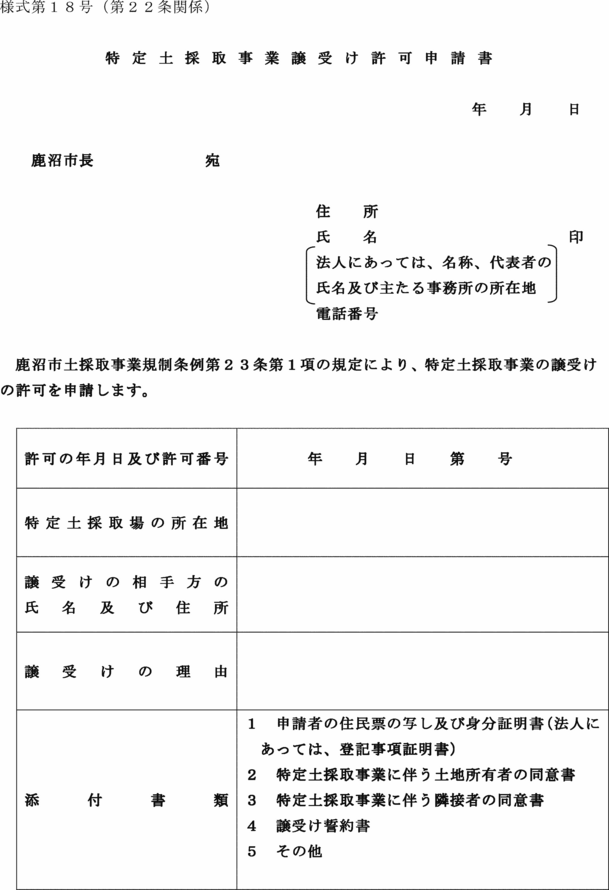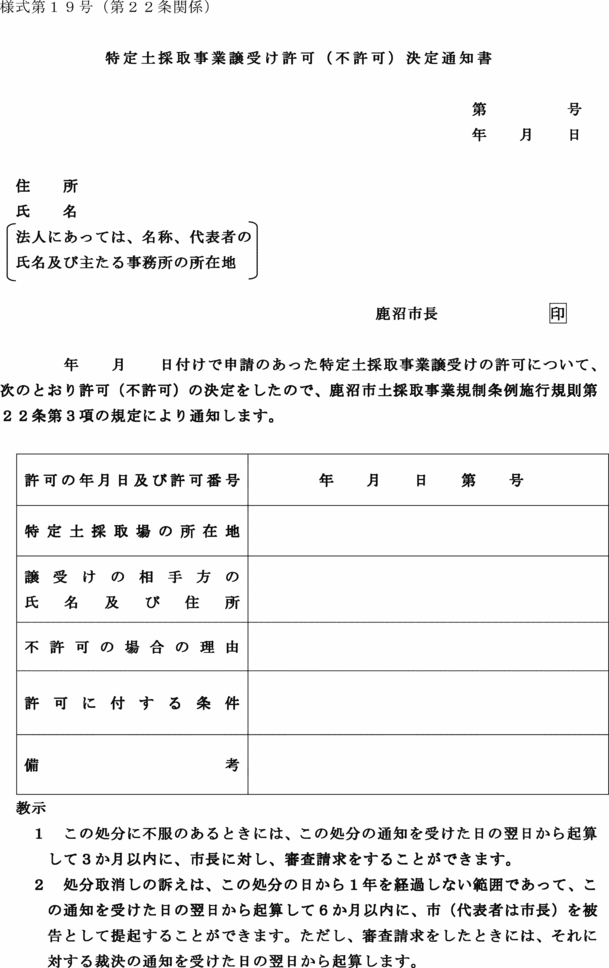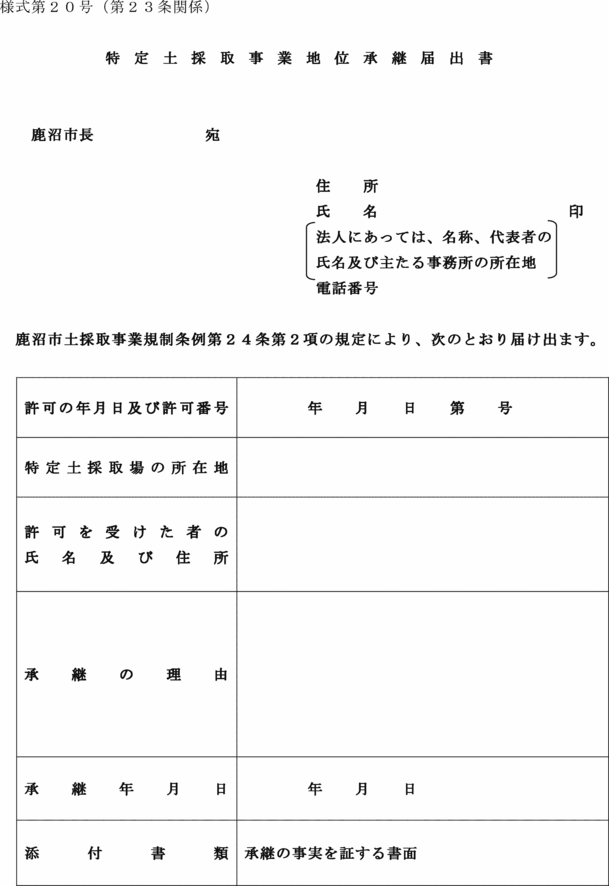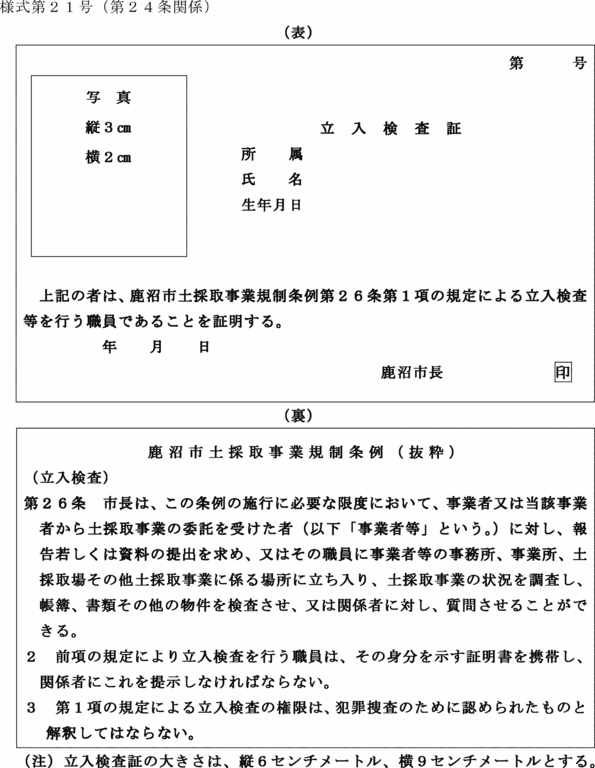第2条 この規則において使用する用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
第3条 条例第3条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 地方住宅供給公社、地方道路公社、日本下水道事業団、土地開発公社及び自動車安全運転センター
(6) 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土採取事業に伴う災害発生の防止等に関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認める者
第4条 条例第3条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる土採取事業とする。
(15) 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第15条第4項の許可に係る土採取事業
(16) 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号)第5条第2項の許可を受けた土採取事業
第5条 条例第3条第3号の規則で定めるものは、次に掲げる土採取事業とする。
(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土採取事業であって、当該区域内で採取した土を当該区域内のみで使用するもの
(2) 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある土採取事業
2 市長は、許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、許可又は不許可について、特定土採取事業許可(不許可)決定通知書(
様式第2号)により当該許可申請書を提出した者に通知するものとする。
第8条 条例第7条第4項の同意を得たことを証明する書面は、土地の所有者に係るものにあっては特定土採取事業に伴う土地所有者の同意書(
様式第3号)とし、隣接者に係るものにあっては特定土採取事業に伴う隣接者の同意書(
様式第4号)とする。
(1) 特定土採取場の位置を示した縮尺5,000分の1以上の地図
(2) 特定土採取場及びその周辺の状況を示した見取図
(3) 特定土採取場から国道又は県道までの経路の平面図
(4) 特定土採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(5) 特定土採取場の土地の採取前の実測平面図及び実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの
(6) 特定土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
(8)
条例の規定及び当該申請に係る土採取計画に従い特定土採取事業を行う旨の誓約書(以下「誓約書」という。)
(10) 特定土採取業者が特定土採取事業の施行に係る工事請負等の契約をした場合は、当該契約書の写し
(11) 特定土採取場の土地の面積及び採取する土の量の計算書
(14) 特定土採取事業の許可申請をした者の住民票の写し及び身分証明書(法人にあっては、登記事項証明書)
(15) 土地の使用権原を証する書類(特定土採取場の土地が自己の所有でない場合に限る。)
(17) 2以上の方向から撮影した特定土採取場の現場写真
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(4) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
(5) 法人でその役員又は使用人のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者のあるもの
(6) 個人で使用人のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者のあるもの
2 市長は、変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、許可又は不許可について、特定土採取事業変更許可(不許可)決定通知書(
様式第6号)により当該変更申請書を提出した者に通知するものとする。
第15条 条例第16条第1項若しくは
第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令又は同条第4項若しくは第5項の規定による是正措置命令は、措置命令書(
様式第12号)によるものとする。
第19条 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定土採取業者の氏名及び住所並びに連絡先(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第20条 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定土採取事業の許可を受けた者の氏名又は名称
第21条 条例第22条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第6条第2項の特定土採取事業許可(不許可)決定通知書
(2) 変更申請書及び第10条第3項の氏名等変更届出書の写し
(3) 第10条第2項の特定土採取事業変更許可(不許可)決定通知書
(4) 第11条の災害等の発生を防止するための措置の届出書の写し
(6) 第17条の特定土採取事業完了(廃止・停止)届出書の写し
(7) 第22条第1項の特定土採取事業譲受け許可申請書の写し
(8) 第22条第3項の特定土採取事業譲受け許可(不許可)決定通知書
(9) 第23条の特定土採取事業地位継承届出書の写し
(1) 申請者の住民票の写し及び身分証明書(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 第8条第1項の特定土採取事業に伴う土地所有者の同意書及び特定土採取事業の許可に伴う隣接者の同意書
(3)
条例の規定及び当該譲受けに係る許可土採取計画に従い特定土採取事業を行う旨の誓約書(以下「譲受け誓約書」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、許可又は不許可について、特定土採取事業譲受け許可(不許可)決定通知書(
様式第19号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
(1) 工法は、平地を掘削する場合にあっては別図第1、斜面を掘削する場合にあっては別図第2に示すところによるものとする。この場合において、掘削又は切土における標準
勾配は、次に掲げる土地の地目に応じ、それぞれ次に定める角度(以下「保安角度」という。)以内に保つこと。
(2) 災害の発生による危険を防止するため隣接地との境界から掘削をする場所までに必要な距離(以下「保安距離」という。)として、1メートル以上の距離を確保すること。ただし、当該掘削をする場所が道路等の公共物件、家屋等に隣接する場合は、保安距離として、2メートル以上の距離を確保することとし、かつ、当該家屋等の基礎部分から5メートル以上の距離を確保すること。
(3) 掘削の深さは、平地を掘削する場合は、掘削する前の地表面から5メートルを限度とし、斜面を掘削する場合は、掘削する場所の周辺の土地の最も低い部分よりも低くしないこと。ただし、平地を掘削する場合において、5メートルを超えても採取する土が確認されるときは、10メートルを掘削の深さの限度とする。
(4) 前号の規定にかかわらず、地下水が
湧出し、付近の地下水脈に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、それ以上掘削しないこと。
ア 現場責任者は、常時、地山の亀裂、陥没等の異常の有無並びに含水及び湧水の状態を監視するとともに、計画的な土の採取に努めること。
イ 作業終了時に、落石又は倒木のおそれのある浮石、立木等がある場合には、直ちにこれらを除去すること。
ウ 気象状況等には常に留意し、危険箇所に対し適切な安全対策をとることができる体制を整備すること。
ア 土の採取中に土砂が流出するおそれがある場合には、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土のう積み、土盛堤、柵等の仮設工を行うこと。
イ 特定土採取事業の完了後においても土砂が流出するおそれがある場合には、擁壁、えん堤その他これらに代わり得る施設を築造し、土砂の流出を防止するための対策を行うこと。
ア 土の採取中に表面水によって法面が洗掘し、又は崩壊するおそれがある場合には、法肩に接する地山に、法肩に沿って素掘溝、コンクリートトラフ等による排水溝を設置し、地山からの流水が法面に流入しないように処置すること。
イ 次号ア(ア)ただし書の規定による埋戻し以外の方法により当該跡地の処理をする場合は、法肩線又は水平面に集排水施設を、法面に縦水溝又は斜水溝を、法面と水平面との接合点に集水桝等を設置することその他円滑な排水をするために必要な処置をとること。
ウ 湧水によって法面が洗掘し、又は崩壊するおそれがある場合には、水抜きのための水平孔、地下排水溝等の施設を設置し、湧水を排除する措置をとること。
エ 湧水及びウの規定により設置した施設が、周辺の土地に害を及ぼさないよう必要な処置をとること。
オ 平地掘削の跡地に雨水、湧水等によって水が貯留し、当該跡地への転落による事故が発生するおそれがある場合には、速やかに排水ポンプを設置し、貯留した水を除去する処置をとること。ただし、付近に放流先がないこと等により貯留した水のくみ上げが困難な場合は、看板の設置その他事故の発生を防止するための措置をもって排水ポンプの設置に代えることができる。
(イ) 埋戻しは、掘削を完了した区域ごとに速やかに行うこと。
(ウ) 埋戻しを行わない特定土採取場の跡地については、有刺鉄線、危険防止柵等の設置その他の危険を防止するために必要な措置を講ずること。この場合において、当該跡地の法面は、高さ5メートルごとに、地目が山林又は原野にあっては幅2メートル以上、地目がそれ以外のものにあっては幅1メートル以上の水平面を、それぞれ設けるとともに、保安角度を保つこと。
特定土採取事業を完了し、又は廃止したときは、土砂の崩壊、流出等を防止し、及び生活環境の保全を図るため、法面に保護工を施工しなければならない。この場合において、粉じんの発生を防止するために必要な措置をとること。
(1) 特定土採取場の標識及び危険防止等の看板は、周辺の住民等が見やすい箇所に設置し、危険の防止について十分な効果を有するものとすること。
(2) 特定土採取場は、関係者以外の者の立入りを禁じ、その周囲をネット柵、とたん塀、板塀等により囲い、かつ、出入口には扉を設け、及び看板を掲げること。
(3) 特定土採取事業の始業時間は午前7時、終業時間は午後6時とする。この場合において、作業中の騒音について隣接者、住民等から苦情があったときは、騒音を防止するために必要な措置をとること。
(4) 特定土採取場からの粉じん、運搬路から生ずるほこり等が周辺の生活環境を害することがないように散水、防じん材の散布、運搬車両の洗車場の設置等の適切な措置をとること。
(1) 運搬車両の公道への出入口等において、交通に支障があるときは、交通整理員の配置、安全施設の設置その他の交通安全に必要な措置をとること。この場合において、通学路等については、特に児童の安全を確保するために必要な措置をとること。
(2) 土を運搬車両に積み込む際には、最大積載量を超えないように留意するとともに、必要に応じて、運搬する土をシートで覆うこと等の粉じんの飛散を防止するための措置をとること。
(3) 路面を汚損した場合には速やかに清掃し、路面を破損した場合には直ちに復旧すること。
(1) 景観その他の見地から保存が必要な樹林については、できる限りその全部又は一部の保存を図るものとする。
(2) 特定土採取場の跡地の法面については、原則として、緑化を図ることとし、周辺の状況及び特定土採取事業の着手前の状態を考慮し、次号から第5号までに定める植草又は植樹を行うものとする。
(3) 土の採取に当たり、山林の一部を伐採し、付近の景観を悪化させた場合は、植草及び植樹を行うことにより、緑地の復元を図るものとする。
(4) 前号の場合以外の場合には、植草又は種子吹付けを行うものとする。
(5) 特定土採取場の跡地の法面は、原則として、植草及び植樹により保護すること。
2 水平面の幅は、地目が山林及び原野にあっては幅2メートル以上、それ以外のものにあっては幅1メートル以上とすること。
2 水平面の幅は、地目が山林及び原野にあっては幅2メートル以上、それ以外のものにあっては幅1メートル以上とすること。

様式第1号
(第6条関係)
様式第2号
(第6条関係)
様式第3号
(第8条関係)
様式第4号
(第8条関係)
様式第5号
(第10条関係)
様式第6号
(第10条関係)
様式第7号
(第10条関係)
様式第8号
(第11条関係)
様式第9号
(第12条関係)
様式第10号
(第13条関係)
様式第11号
(第14条関係)
様式第12号
(第15条関係)
様式第13号
(第16条関係)
様式第14号
(第17条関係)
様式第15号
(第18条関係)
様式第16号
(第19条関係)
様式第17号
(第20条関係)
様式第18号
(第22条関係)
様式第19号
(第22条関係)
様式第20号
(第23条関係)
様式第21号
(第24条関係)