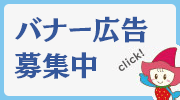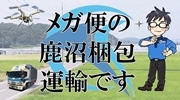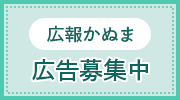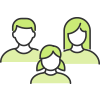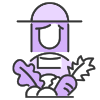国保の給付
国保の担当窓口に申請すれば、かかった医療費の一部をあとで払い戻してもらったり、現金の支給を受けられるものがあります。
ただし、法律の規定によって国保税の未納額がある場合は、これらの給付が受けられないこともありますのでご注意ください。
- 医療費が高額になるとき(高額療養費・限度額適用認定証 など)
- 出産したとき
- 亡くなったとき
- 特定疾病をお持ちの方
- 医療費を全額負担したとき
掲載日 平成22年11月5日
更新日 令和4年4月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険給付係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206