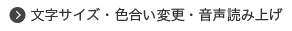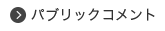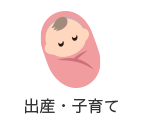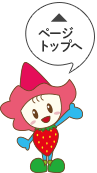帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用の一部助成について
令和7年4月1日から帯状疱疹ワクチンは定期予防接種となります。
接種を希望する方は、制度やワクチンの種類について確認いただき、接種をご検討ください。
鹿沼市では対象となる方の予防接種費用の一部を助成します。
ただし、 過去に自費や鹿沼市の助成を受けて対象となるワクチンを接種している人は助成の対象にはなりません。
また、帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成について令和7年度は継続します。
定期予防接種対象者ではない人で、接種を検討している方はこちらのページを参照ください。
帯状疱疹ワクチン受診券の訂正について
帯状疱疹ワクチン受診券の委託医療機関一覧に誤りがありました。
誤記によりご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございませんでした。お詫びして訂正いたします。
| 医療機関名 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 誤 | かぬま皮膚科・美容皮膚科クリニック |
77-5950 |
| 正 | かぬま皮膚科・美容皮膚科クリニック | 60-1300 |
定期予防接種の対象者について
鹿沼市に住所があり、以下に該当する人が対象です。ただし、過去に自費等で帯状疱疹ワクチンを接種したことがある人は対象外です。
- 今年度に65歳になる人
- 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある人(障害者手帳1級相当)
- 今年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる人
- 3.は5年間の経過措置(令和7年4月1日から令和11年度まで)により、各年度で該当する方が対象者となります。
- 101歳以上の人は令和7年度のみ対象者となります。
- 年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる人等)で該当の年齢になる方が対象者となります。
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和35年(1960年)4月2日~昭和36年(1961年)4月1日 |
| 70歳 | 昭和30年(1955年)4月2日~昭和31年(1956年)4月1日 |
| 75歳 | 昭和25年(1950年)4月2日~昭和26年(1951年)4月1日 |
| 80歳 | 昭和20年(1945年)4月2日~昭和21年(1946年)4月1日 |
| 85歳 | 昭和15年(1940年)4月2日~昭和16年(1941年)4月1日 |
| 90歳 | 昭和10年(1935年)4月2日~昭和11年(1936年)4月1日 |
| 95歳 | 昭和5年(1930年)4月2日~昭和6年(1931年)4月1日 |
| 100歳 | 大正14年(1925年)4月2日~大正15年(1926年)4月1日 |
| 101歳以上 | 大正14年(1925年)4月1日以前にお生まれの方 |
- 対象者には助成対象となる年度の4月に受診券を発送しました。
- 高齢者肺炎球菌予防接種とは対象者が異なりますのでご注意ください(高齢者肺炎球菌は接種日時点で65歳の人が対象)
ワクチンの種類と助成金額について
|
名称
|
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」 |
| 種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
|
接種できない人 |
・病気や治療によって免疫が低下している人 ・60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある人(障害者手帳1級該当) |
免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
| 接種に注意が必要な人 |
他の生ワクチンを接種した人は、27日以上の間隔を置いて接種してください。 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた人は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 |
筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する人、抗凝固療法を実施されている人は注意が必要です。 |
| 接種回数 | 1回 |
2回 <シングリックスの標準的な接種間隔> 1回目の接種から2か月後に2回目を接種する ※2か月を超えた場合であっても、6か月後までに2回目の接種を推奨します。 |
| 助成金額 | 4,000円/回 | 10,000円/回 |
| 接種方法 | 皮下接種 | 筋肉内接種 |
| ワクチンの効果 |
(帯状疱疹に対して) 接種後1年時点:6割程度の予防効果 接種後5年時点:4割程度の予防効果 接種後10年時点:- |
(帯状疱疹に対して) 接種後1年時点:9割程度の予防効果 接種後5年時点:9割程度の予防効果 接種後10年時点:7割程度の予防効果 |
| 副反応 |
注射部位の局所症状(赤み、かゆみ、熱くなる、腫れ、痛み、硬くなる)、発疹、倦怠感などが報告されています。また非常にまれですが、アナフィラキシー(全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しいなど)や、血小板減少性紫斑病(鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくいなど)、無菌性髄膜炎(発熱、吐き気、頭痛、うなじがこわばり固くなって首を前に曲げにくいなど)がみられることがあります。 |
注射部位の痛み、赤み、腫れなど、全身症状として筋肉痛、疲労感、頭痛を伴うことがありますが、これらの多くは、通常3日間ほどで消失します。また、重大な副反応として、ショックやアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する血圧低下、呼吸困難や全身性のじんましんを伴うアレルギー反応のこと)が起こる可能性があります。 |
※定期接種対象年齢で生活保護受給中の方は、全額助成(無料)となります。接種時に生活保護法による医療扶助受給資格者証を医療機関にご提示ください。
定期予防接種を受けるには
接種をご希望の方は、直接医療機関へご予約ください。
接種料金は各医療機関で設定していますので、医療機関へお問い合わせください。
接種時は、受診券を医療機関へお持ちください。
委託医療機関で接種する場合
委託医療機関以外で接種する場合
(1)栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業の接種協力医療機関で接種する場合
医療機関でお支払いの際、接種料金から助成額を差し引いた残りの金額が請求されますのでお支払い下さい。(市役所への申請は必要ありません)
接種協力医療機関は、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
接種を希望する方は、予防接種を行う前に![]() 帯状疱疹の予防接種についての説明書(pdf 258 KB)をご一読ください。
帯状疱疹の予防接種についての説明書(pdf 258 KB)をご一読ください。
(2)(1)以外の医療機関で接種する場合
事前の申請が必要です。健康課にお問合せ下さい。事前申請の方法についてはこちらををご覧ください。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、過去に水ぼうそうにかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスを原因として起こります。加齢や疲労、ストレスなどによって免疫力が低下すると、ウイルスは活性化し帯状疱疹を発症します。帯状疱疹を発症すると、体の片側に水疱(みずぶくれ)を伴う紅斑(発疹)が帯状に広がります。症状は、痛みを伴うことが多く、3~4週間ほど続きます。皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(postherpetic neuralgia:PHN)と呼ばれる長期間にわたる痛みが続くことがあります。PHNには根本的な治療方法がなく、何か月、ときには何年も強い痛みが残ってしまうことがあります。50歳以上では、帯状疱疹を発症した人の約2割がPHNに移行するといわれています。
健康被害について
万が一重篤な副反応が起こった場合は、予防接種法による救済の対象とはなります。
医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。