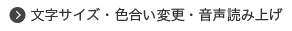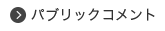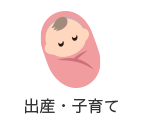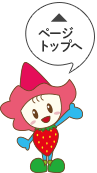農業者年金
農業者年金は、農業者の老後生活の安定と意欲ある担い手の確保に資する重要な制度となっています。
農業者年金制度について
加入について
年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、または60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者の方であれば、どなたでも加入できます。農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
加入と脱退は任意
加入も任意ですが脱退も自由です。脱退された場合には脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と運用益は、加入期間にかかわらず(例え1か月の加入でも)、将来、年金として支給されます。脱退された方も、加入要件を満たしていればいつでも再加入できます。
積立方式の年金です
納付した保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型の年金です。運用は長期的に安定を重視したものとなっています。
保険料は自由に決めることができます
月額2万円(35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)から6万7千円の間で、千円単位で自由に決められます。経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。
税制面の優遇措置
納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象で、将来受け取る年金は公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。
また一般の預貯金等の利子には約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分年金原資が多くなります。
保険料に対する助成があります
最低保険料2万円の負担が困難な場合には国庫補助の仕組みがあります。次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。
- 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
- 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
- 認定農業者・認定新規就農者で青色申告者、またはそれに準じるなど条件を満たしている方
終身年金で80歳までの保証があります
年金は終身受給できます。仮に80歳前に死亡した場合でも、死亡月の翌月から80歳までに受け取る年金総額(国の助成分を除く)の現在価値に相当する額が一時金として遺族に支給されます。
受給できる年金は2種類
農業者老齢年金
自分が納めた保険料とその運用実績を基礎とした年金で、保険料を納付した方が受給できます。
原則65歳からの受給ですが、希望により60歳まで繰上受給することもできます。
特例付加年金(旧制度では経営移譲年金)
保険料の助成を受けた方が対象で、助成分とその運用実績を基礎とした年金です。受給するためには農業経営から引退(経営継承)する必要があります。
65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本ですが60歳まで繰上受給することもできます。また、経営継承には年齢制限はありませんので65歳以降に受給を開始することもできます。
現況届の提出
現況届は年金を受給するために毎年必要な手続きで、提出がない場合は年金の支給が一時停止されます。
提出期限は毎年6月末日で、受付は農業委員会事務局または各コミュニティセンターで行っています。
農業者年金受給者の住所変更や死亡した場合
住所が変わった場合などは、速やかにJA(農協)で手続きをしてください。
受給者が死亡した場合は、速やかに死亡届をJA(農協)に提出してください(必要書類:印鑑、年金証書、戸籍謄本)。提出が遅れると過払いとなった年金の返納が必要となることがあります。
特例付加年金・経営移譲年金を受給の方は次のことに気をつけて下さい
農地の異動に十分注意しましょう
経営移譲(経営継承)により貸していた農地が返還されたり農地以外に転用したりすると、年金が支給停止になることがあります。
貸借の相手先変更や農地転用など、農地の異動の予定がある時は、必ず事前に農業委員会に相談してください。
農業経営に関する名義変更を確認
農業経営に関する各種の名義が経営移譲の相手先(後継者や第三者)にきちんと変更されていることを確認しましょう。
(1)農業共済関係名義
(2)転作助成金・経営所得安定対策交付金の申請者名義
(3)農業所得に関する納税申告者名義
(4)土地改良区の組合員名義
(5)農業協同組合の組合員名義 (第三者への経営移譲の場合は(1)と(2)のみ)
お問い合わせ
農業者年金の内容や加入申込みについて、ご不明な点があれば農業委員会事務局か、お近くのJA支店へご相談ください。
詳しくは独立行政法人農業者年金基金ホームページをご覧ください。